2歳児の子育てをしていると、こんな悩み出てきませんか?
- お菓子の味を知ってしまって、ご飯を食べなくなった。
- どうしたらご飯を食べてくれるかわからない。
- できるだけ楽に、この時期を乗り越えたい!
僕にも3歳の息子がいますが、ご飯を食べずにお菓子ばかり食べる息子にイライラしたり、ストレスや疲れで「育児しんどい…」と何度も思ってました。
 読者
読者ご飯をしっかり食べてほしい..どうすればいい?
そこで本記事では、100名のママに、2歳の子供の「お菓子ばかりでご飯を食べない問題」の解決策を聞いてきました。以下アンケートの結果です。
2歳の子供がご飯を食べてくれた作戦
- ご飯を子どもと一緒に作る
- 事前にお菓子をいつあげるか約束する
- 子どもが好きなメニューを作る
- エンタメ性のある設定
- 自然素材のお菓子をあげる
- ご飯を可愛く盛りつける
- 友達がご飯を食べている様子を見せる
- ご飯を食べたらご褒美をあげる
「もっと楽に子どもご飯を用意したい」人は、管理栄養士が監修している宅配の幼児食がおすすめ!使うだけで精神的に楽になれますよ!



僕のおすすめは、無添加で価格が安いモグモ!
▼以下のランキング記事で幼児食とモグモを紹介してるから参考にしてみてください!
2歳の子供がご飯を食べずお菓子ばかりになる原因は?


この章では、100名のママに「お菓子ばかり食べるようになったきっかけ」を教えてもらいました。多くの家庭で共通していた原因を紹介します。



お菓子問題は、絶対にさけては通れない道!罪悪感を感じる必要はないからね。
お兄ちゃんやお姉ちゃんの真似



お兄ちゃん・お姉ちゃんの真似をしたがるようになり、お菓子の種類や食べる量に変化がでてきたこと。「あれがしたい!これがしたい!」と言葉で感情を表現できるようになったこと。



上の子が食べているお菓子を見て、弟が欲しがるようになりました。最初は「まだ早いかな」と思い食べさせないようにしていましたが、ある日、兄がこっそり弟に分けていたことが判明…。それ以来「ご飯はいらない、お菓子がいい!」と主張するようになってしまいました。
食欲がないときにあげた



風邪でご飯をあまり食べられなかったとき、ゼリーやビスケットなら口にしてくれたので、ついそればかりあげていました。治った後も「ご飯はイヤ、お菓子がいい」と言うようになり、癖になってしまったようです。



風邪でご飯をあまり食べられなかったとき、ゼリーやビスケットなら口にしてくれたので、ついそればかりあげていました。治った後も「ご飯はイヤ、お菓子がいい」と言うようになり、癖になってしまったようです。
ご褒美としてあげた



ご飯を食べている最中に、「食べ終わったらおやつがあるよ」と言ってしまった事がきっかけです。何も考えずについ言ってしまった言葉でしたが、おやつに意識が向いてしまうので言うべきではありませんでした。。



「ご飯を食べたらおやつがあるよ」と何気なく言ってしまったこともありました。その結果、ご飯よりおやつに意識が向いてしまい、食事中も「早くお菓子食べたい」とばかり言うようになってしまいました。
【成功談】お菓子ばかりでご飯を食べない2歳の子供に効いた神業


2歳児は親が用意したご飯を食べずに、お菓子ばかりを欲しがる子も少なくありません。お菓子をあげないと泣き叫んだり暴れたり大変ですよね。
そこでこの章では、先輩ママが試したご飯を食べない2歳の子供に効果があった作戦をまとめました。
それぞれ口コミを紹介します。
子供と一緒にご飯を作る



子どもにニンジン入りのシチューを食べさせる前に、調理前のニンジンを触らせて「これを切って料理するんだよ」と伝えたところ、納得して素直に食べてくれました。



食事前に子ども用のミニしゃもじでご飯を混ぜたり、型抜きで野菜を抜いたりと簡単なお手伝いを経験させると、「自分が作ったご飯」という意識から箸を進めるように。
事前にお菓子をあげるタイミングを約束



ご飯を食べ終わったらお菓子を食べていいというルールを決めました。最初は「ご飯よりお菓子!」でしたが、繰り返すうちにご飯を先に食べてくれるように。食べ終わる頃にはお腹がいっぱいで、お菓子を欲しがらなくなることも増えました。



「おやつ=食後のお楽しみ」と家族で統一ルールを作り、干し芋やおにぎりなど自然素材のおやつに切り替えました。さらに、一緒にご飯を作る機会を増やすことで「自分が作ったご飯」を食べる楽しさが出てきました。



「おやつ=食後のお楽しみ」と家族で統一ルールを作り、干し芋やおにぎりなど自然素材のおやつに切り替えました。さらに、一緒にご飯を作る機会を増やすことで「自分が作ったご飯」を食べる楽しさが出てきました。
子どもが好きなメニューを用意



とにかく食べてほしかったので、子どもが好きなメニューを中心に出しました。我が家はうどんと野菜が好きだったので、そればかり用意して気分が乗ったらおかわりを自由にさせました。お腹がいっぱいになるとお菓子を欲しがらなくなることも多かったです。



ハンバーグやコロッケは食べるので、そこに細かくした野菜を混ぜました。納豆やふりかけ、海苔を使って食べやすくする工夫も。どうしても食べない時は、さつまいもや枝豆、バナナなど食べられるものだけ食べさせてゼリーでしめる日もありました。
食事にエンタメ要素を取り入れる



お気に入りのお人形がスプーンを持って食べさせてくれるふりをすると大喜び!「お人形と一緒に食べる」感覚で、楽しく完食できました。



「ご飯を食べると動物に変身できる魔法の薬」という設定にして、ひと口食べるごとに動物の名前を出しながら食べてもらいました。立ち食いでもOKにして、食べることを楽しい遊びにしたら、完食できる日が増えました。



キャラクターの形のおにぎりや、カラフルな食材を少しずつ並べて“選べるバイキング風”にすると興味を持ってくれました。ママが笑顔で食べる姿を見せるのも効果大でした。
自然素材のお菓子を選ぶ



おやつの内容を見直し、野菜や果物を小さく切ったものをお菓子感覚で与えるようにしました。おやつの時間を決めて大人も一緒に食べるようにし、ご飯はお子さまランチ風のワンプレートに。最後にデザートを一緒に盛り付けることで「食事の一部」として受け入れてくれるようになりました。



栄養のあるものを与えたかったので、果物を小さく切ってお菓子みたいにして与えたらよく食べてくれました。
ご飯を可愛く盛りつける



いろんな味付けを試したり、キャラクターかまぼこやカラフルなお弁当カップを使ったりして、見た目で楽しませました。小袋のお菓子を「これを食べたらご飯ね」と約束して渡すようにしたら、少しずつご飯も食べるようになりました。



ご飯を一口サイズのおにぎりにして顔をつけたり、にんじんを型抜きして可愛くしたら、見た目に惹かれて食べてくれるように。甘めの味付けにするとさらに食いつきがよかったです。
友達がご飯を食べる様子を見せる



親子だけだと食べることを嫌がるのに、同年代の友達と一緒だと競うように食べてくれました。外食で楽しい雰囲気の中で食べる経験が、家でも食事に前向きになるきっかけになりました。
ご飯を食べたらご褒美をあげる



キャラクターのシールを用意し「ご飯を食べたら1枚貼れるよ」とルールを作ったら、「全部食べたよ!」と嬉しそうに完食する日が増えました。しばらく続けると、シールがなくても食べられるようになりました。



小袋のお菓子を「全部食べたら1袋あげる」という形にしたら、野菜も残さず食べるようになりました。我が家の子にはこの方法が一番効果がありました。
【意味なし】お菓子ばかりでご飯を食べない2歳の子供に逆効果だった作戦は?


「ご飯を食べてほしい…!」そんな思いから、ついやってしまった作戦が裏目に出ることもありますよね。ここでは、先輩ママ・パパたちが実際に試してみて「これは逆効果だった…」方法を紹介します。
- お菓子はご飯食べてから!
- 無理やりご飯を食べさせる。
- お菓子を食べたらダメ!
- 感情的に怒る。
それぞれ口コミを紹介します。
お菓子はご飯食べてから!



朝食の前からお菓子を欲しがるようになったので、最初は「ダメよ、ご飯を食べてから」と言っていたが言うことを聞かずに泣き叫ぶので、あきらめた。小さなゼリーやおせんべいなどを1個だけあげるから、ご飯を食べるのよと妥協すると、それからご飯を食べるようになったので、子どもの言い分を少し聞き入れるのも手だと思います。



ご飯を食べないとおやつ抜きだよ。は全く意味なかった。むしろうちの子はおやつをしっかりあげるほうがご飯食べてくれるようになった。
無理やりご飯を食べさせる



なんで食べないのかイライラして無理に食べさせると子供も食べることを嫌がるようになる。少しでも口にしてくれれば良いと諦めるのも大事。



無理に食べさせようと怒ったらますます拒否されてしまいました。
ご褒美でお菓子を約束する作戦も、逆にお菓子への執着が強くなってしまい逆効果でした。
お菓子を食べたらダメ!



「お菓子を食べたらダメ」と強く叱ってしまったことが逆効果で、余計に隠れてお菓子を食べたり、反発するようになってしまいました。また、ごはんの量を無理に増やしたりすると余計にイヤイヤが激しくなったため、「一口でもOK」「楽しい食卓づくり」を意識した方がうまくいきました。



あまり効果がなかったのは、「ご飯を食べないとお菓子はダメ」と強く制限する方法でした。逆にお菓子への執着が強くなり、泣いてしまって余計に食事が進まなくなりました。また無理に口へ運ぼうとした時も拒否が強まり、食卓が険悪な雰囲気になってしまった経験があります。やはり怒るよりも工夫で興味を持たせる方が大事だと感じました。
感情的に怒る



子供が食べなくなった時についカッとしてしまい感情的に怒ってしまったことがありました。しかしまだ2歳なので、どうして怒られているかがあまりよく分かっていなかったようでした。感情的に怒るのは解決にもならず1番良くないと思ったのでそれ以降はなるべく怒らないようにしています。



どうしても食べてくれないと、イライラしちゃって、怒ってしまうことがありましたが、よけい嫌な気持ちにさせてしまっていたので、ご飯の時はおこならいようにしていました。
【コレ神!】ご飯を食べない2歳の子供に試してほしい幼児食!


ここまで、先輩ママ達の「ご飯を食べてもらえた成功談」を伝えてきましたが、「もう疲れた、限界!」という瞬間は必ず訪れます。
ここでは、同じ経験を何度もしてきた僕が、今まで試してきた中で最高に良かった幼児食を紹介します。



もし迷ったらモグモがおすすめだよ
他の幼児食や離乳食も含めたサービスを知りたい人は、以下も参考にしてみてくださいね。
モグモ|完食率が高く価格も安い!


\初回は8食2,980円でお試し可能/
※解約手数料は一切かかりません
モグモは、1歳半〜6歳の幼児向けに開発された冷凍の幼児食サービスです。管理栄養士が監修した約40種類以上のメニューを、パウチに入った状態で冷凍配送。


電子レンジで温めるだけで、栄養バランスの取れた幼児食が完成します。





モグモは全品無添加だから子どもに与えても安心!
モグモの価格は1食あたり372円で元々お試ししやすい価格ですが、初回はなんと8食2,980円で購入できます。
2歳児のご飯を作るの疲れた…というママは一度検討してみてください。
| モグモのメリット | モグモのデメリット |
|---|---|
| 子どもと楽しめる喜ぶ工夫がいっぱい! 完食率が高かった! ほかの幼児食と比べて、価格が圧倒的に安い! 完食率が高かった! | 塩分がやや高い 食べ盛りには量が少ない 営業メールが多い パンの調理がめんどくさい |
もっと詳しく知りたいという方は、こっちの記事も参考にしてみてね。
ホーミール|国産素材と低塩分


\初回は1食399円でお試しできる!/
※解約手数料は一切かかりません
ホーミールも管理栄養士が監修している冷凍の幼児食ですが、その特徴は1食あたりの塩分量が1g以下、そして国産素材を中心に使っている点です。



子どもの味覚が形成される大事な時期だから、塩分控えめは助かる!


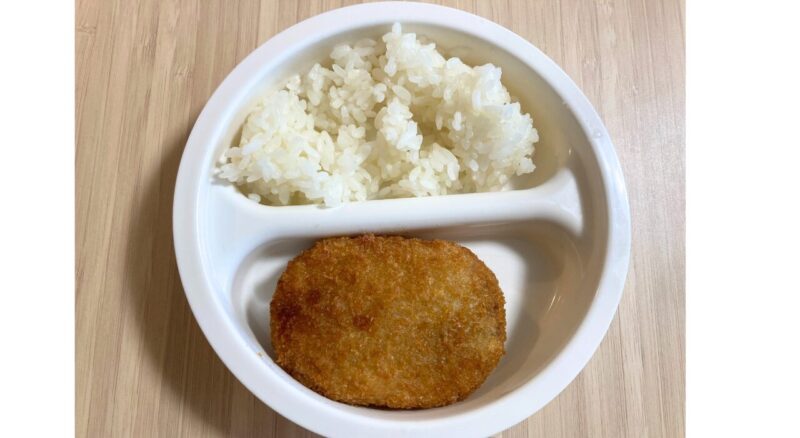
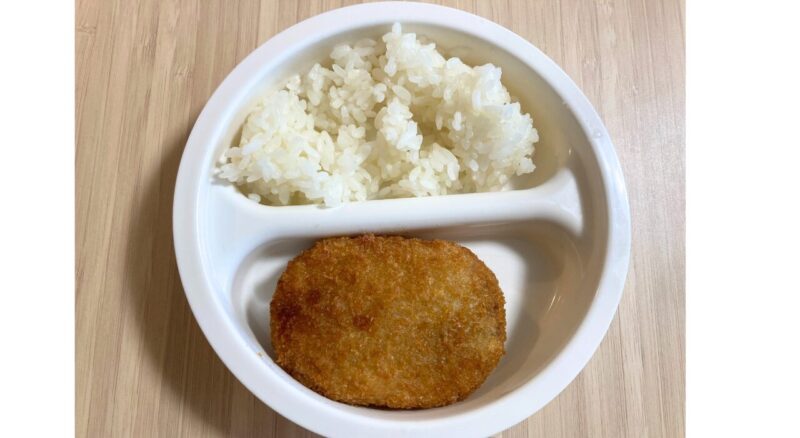
4歳児以上には量が少ないですが、2歳児であれば十分な量です。
値段はモグモより少し高めですが初回は3,980円でお試しできるので、お守りフードとしてストックしてみては?
| ホーミールのメリット | ホーミールのデメリット |
|---|---|
| 低塩分で、子供の味覚を育てられる! 月齢ごとにメニューが用意されている 無添加で、国産素材が中心! 初回のトライアル価格が激安! | 返金制度はない。 |
ホーミールは以下の記事でも解説しています!
つくりおき.jp|家庭的な味とタイパ最強


\ 手抜き感なく楽できる♪/
※解約手数料・年会費はかかりません
つくりおき.jpは、シェフと管理栄養士が監修している冷蔵の幼児食です。全メニュー幼児向けに取り分けできるので、離乳食完了期(1歳半頃)から大人まで家族全員で食べられるのが大きな特徴です。



つくりおき.jpは、手作り感がパンパない!


実家を思い出す家庭的でやさしい味つけ。冷凍食品と比べて、食卓に出しても罪悪感はありませんでした。
デメリットは1食あたりの価格が798円とやや高いこと。ただ、大人も同じメニューが食べられるので食卓がつくりおき.jpで完結できるのはメリットです。



タイパ面で考えると、つくりおき.jpが1番おすすめ!
| 良い口コミ | 悪い口コミ |
|---|---|
| 冷蔵で美味しい! 小分けになっていて使い勝手◎ 自分で作れないメニューを食べられる 食卓に出しても罪悪感がない | 少し割高い 2人では食べきれない ダンボールが開けずらい 冷蔵庫のスペースが必要 |
もっと詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。
2歳児の「ご飯食べない」は、どこもパパ・ママもぶち当たる問題。僕もかなり苦労しましたが、幼児食で救われた部分が多々ありました…!
「冷凍食品だと罪悪感を感じる..」という人は、管理栄養士が監修している幼児食を一度検討してみてください。



みんなで2歳児の育児を乗り越えよう!
子どもがご飯を食べてくれた作戦
- ご飯を子どもと一緒に作る
- 事前にお菓子をいつあげるか約束する
- 子どもが好きなメニューを作る
- エンタメ性のある設定
- 自然素材のお菓子をあげる
- ご飯を可愛く盛りつける
- 友達がご飯を食べている様子を見せる
- ご飯を食べたらご褒美をあげる






コメント